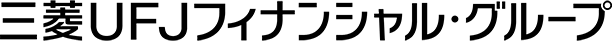気候変動に関するリスク -移行リスク・物理的リスク-
気候変動に関するリスクには、気候関連の規制強化や脱炭素技術移行への対応といった脱炭素社会への移行に伴うリスク(移行リスク)と、気候変動に伴う自然災害や異常気象の増加等によってもたらされる物理的な被害に伴うリスク(物理的リスク)の2つがあります。
金融機関は、これらのリスクについて、自社の事業活動への直接的な影響と、与信先が影響を受けることに伴う間接的な影響の両方に対応する必要があります。
MUFGは、TCFDの提言を踏まえ、主要なリスク分類ごとの移行リスクおよび物理的リスクの事例について整理しました。なお、短期・中期・長期といった時間軸に関してもリスク分類ごとに整理をしています。
また、自然災害や異常気象の増加等により社員や保有資産が被災するリスクを想定し、事業継続に向けた各種訓練や事業継続計画(BCP)策定等の対策を講じています。
移行リスクの例 |
|
|---|---|
政策と法規制 |
・炭素税の導入によるGHG排出量によるコスト増加 ・排出量報告義務の強化 ・既存の製品・サービスに関する規制 ・訴訟の対象 |
テクノロジー |
・GHG排出量の少ない製品・サービスへの転換 ・新技術への投資が頓挫 ・低排出技術への移行コスト |
市場 |
・顧客行動の変化 ・市場シグナルの不確実性 ・原材料価格の上昇 |
評判 |
・消費者の嗜好の変化 ・セクターの偏狭化 ・ステークホルダーの関心の高まりやステークホルダーへのネガティブなフィードバック |
物理的リスクの例 |
|
|---|---|
| 急性 | ・台風や洪水などの極端な気象現象の深刻度の増加 |
慢性 |
・降水パターンの変化と気象パターンの極端な変動 ・平均気温の上昇 ・海面上昇 |
移行リスク・物理的リスクの影響事例
MUFGは、気候変動から生じる移行リスクおよび物理的リスクについて、主要なリスクの分類ごとの影響事例(潜在的なリスクの事例)を整理しました。
リスクの分類は、以下に示す6つのカテゴリーを中心に整理しています。今後、環境変化に応じて、リスクの分類や各種事例について見直しを行います。
■移行リスクおよび物理的リスクの事例
リスク分類 |
移行リスクの事例 | 物理的リスクの事例 | 時間軸(注) |
|---|---|---|---|
信用リスク |
・政策、規制、顧客の要請、技術開発の変化に対応できないことによる、顧客の事業や財務への影響 | ・異常気象による顧客資産への直接的な損害や、サプライチェーンへの間接的な影響に伴う、顧客の事業や財務への波及 | 短期~長期 |
市場リスク |
・脱炭素社会への移行の影響を受ける産業に関連する保有有価証券や、それに派生する金融商品等の価値の変動 | ・異常気象の影響による市場の混乱、それに伴う保有有価証券等の価値の変動 ・異常気象の影響に対する市場参加者の中長期的な見通しや期待が変化することによる保有有価証券等の価格の変動 |
短期~長期 |
流動性リスク |
・移行リスクへの対応の遅延などによる自社の信用格付の悪化を受けての市場調達手段の限定、それに伴う再資金調達リスクの上昇 | ・異常気象で被災した顧客の復旧・復興に向けた預金引出・コミットメントライン利用に伴う資金流出の増加 | 短期~長期 |
| オペレーショナルリスク | ・CO2削減対策や事業継続性強化のための設備費用の増加 | ・異常気象による被災に伴う本支店やデータセンターにおける業務の中断 | 短期~長期 |
評判リスク |
・カーボンニュートラルに向けた計画や取り組みが外部ステークホルダーから不適切または不十分と評価されることによる評判の悪化 ・環境への配慮が不十分な取引先との関係継続や、自社の移行が遅延することによるMUFGの評判悪化、雇用への影響 |
・異常気象の影響を受けた顧客やコミュニティへの支援が不十分であることによる評判の悪化、事業の中断 | 短期~長期 |
戦略的リスク |
・脱炭素社会への移行に向けた公約を遵守しないことで、MUFGの評判に影響を与え、戦略の遂行へネガティブに影響 | ・異常気象からの直接的な影響や、長期計画への適切な反映を怠ることによる戦略・計画の未達 | 中期~長期 |
- 短期:1年未満、中期:1年~5年、長期:5年超
シナリオ分析
TCFD提言では、気候変動に関するリスクに対する企業の計画や戦略の柔軟性、レジリエンスを示すために複数のシナリオを用いたシナリオ分析の実施を推奨しています。MUFGは、国連環境計画・金融イニシアティブ(UNEP FI)が主導し、気候関連財務情報開示に関する方法論等の検討・開発を目的に実施しているパイロット・プロジェクトに2019年より参画しました。パイロット・プロジェクトによる検討の結果も踏まえ、移行リスクについて2050年まで、物理的リスクについて2100年までを対象とした分析を実施しました。
シナリオ分析の実施に際しては、上記パイロット・プロジェクトによる検討結果に加え、外部専門家による検証結果も反映しています。また、規制当局とも対話をしつつ、分析手法の高度化に向けた検討を継続的に実施しています。
■移行リスク
・シナリオ分析のプロセス

・対象セクター
| 対象セクター |
|---|
エネルギー(国内、海外)/ユーティリティ(国内、海外)/自動車(国内、海外)/鉄鋼(国内、海外)/空運(国内、海外)/海運(国内、海外) |
・手法・結果
計測手法には、UNEP FI のパイロット・プロジェクトでの検討結果を踏まえ、個社レベルのボトムアップ手法とセクターレベルのトップダウン手法を組み合わせて影響を評価する統合的アプローチを採用しました。
シナリオは、IEAにより公表されている「持続可能な開発シナリオ(2°C(未満)シナリオ)」に加えて、NGFSシナリオを前提とし、2°C(未満)シナリオに加えて、1.5°Cシナリオについても対象に、各シナリオにおける信用格付への影響を分析するとともに、当該セクターの与信ポートフォリオ全体の財務インパクトの影響について分析を実施しました。
| シナリオ | ・IEAによる「持続可能な開発シナリオ(2°C(未満)シナリオ)」、NGFSが公表した1.5°Cシナリオを含む複数のシナリオ |
|---|---|
分析手法 |
・個社レベルのボトムアップ手法とセクターレベルのトップダウン手法を組み合わせて影響を評価する統合的アプローチを採用し、各シナリオにおける信用格付への影響を分析するとともに、当該セクターの与信ポートフォリオ全体の財務インパクトの影響について分析 |
| 対象セクター | ・エネルギー、ユーティリティ、自動車、鉄鋼、空運および海運セクター |
| 対象期間 | ・2022年3月末を基準とし、2050年まで |
| 分析結果 | ・単年度ベース15億~285億円程度(注) |
- 2023年3月末基準でも著変なし
・今後の移行リスク低減に向けた対応
- お客さまとのエンゲージメントの継続実施
- サステナブルファイナンスやGHG排出量可視化・戦略策定支援等を通じた、お客さまの脱炭素化に向けた取り組み支援
- 規制当局や各種政策委員会、外部有識者等を通じた積極的な議論の実施
- NZBA等の外部イニシアティブにおける議論への積極的な参加
■物理的リスク
・シナリオ分析のプロセス

・結果
気候変動による物理的な被害に伴うリスクのうち、日本をはじめ近年特に発生頻度、被害状況とも顕著である水害を対象に、その発生による与信先のデフォルト確率を用いて、与信ポートフォリオ全体への影響を計測するアプローチを採用しました。
気候シナリオは、IPCCにて公表されている、第5期結合モデル相互比較計画(Coupled Model Intercomparison Project 5:CMIP5)によるRCP2.6(2°C シナリオ)・同8.5(4°C シナリオ)シナリオを前提とし、主に水害が頻発化、大規模化すると想定されるRCP8.5シナリオについて、さまざまな機関より提供を受けたデータ(注)を用いて水害発生時の被害推定の分析を実施しました。
財務インパクトの計算においては、UNEP FI パイロット・プロジェクトでの議論を踏まえ、業務停止期間や保有資産の毀損等を反映しています。
- 出典:Hirabayashi Y, Mahendran R, Koirala S, Konoshima L, Yamazaki D, Watanabe S, Kim H and Kanae S (2013)
Global flood risk under climate change. Nat Clim Chang., 3(9), 816- 821.doi:10.1038/nclimate1911.
| シナリオ | ・気候変動に関する政府間パネル(IPCC)にて公表されているRCP2.6(2°Cシナリオ)、同8.5(4°Cシナリオ) |
|---|---|
分析手法 |
・水害発生時の被害推定の分析を実施し、水害の発生が与信先に与えるデフォルト確率の変化を用いて与信ポートフォリオ全体への影響を計測するアプローチを採用 ・財務インパクトの計算においては、与信先の業務停止期間や保有資産の毀損等を反映 |
| 分析対象 | ・水害 |
| 対象期間 | ・2022年3月末を基準とし、2100年まで |
| 分析結果 | ・累計1,155億円程度(注) |
- 2023年3月末基準でも著変なし